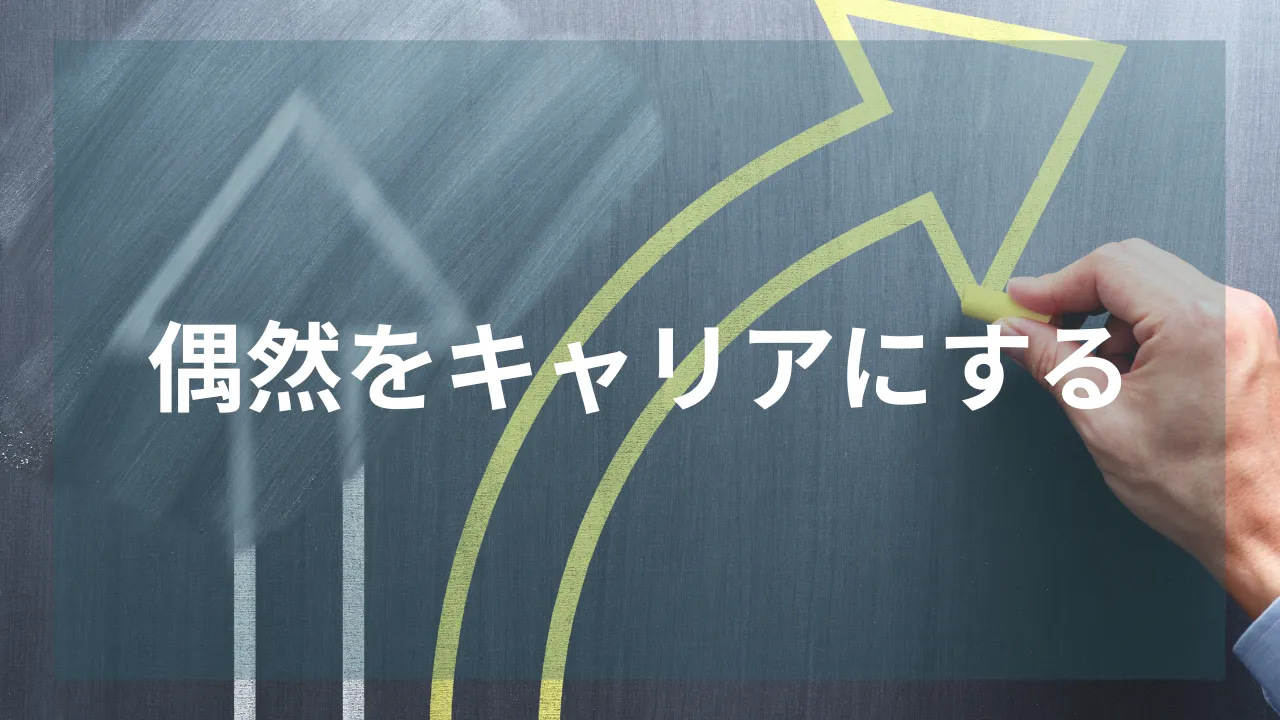キャリアを考えるとき、多くの人は「自分の適性に合った職業を探す」ことに意識が向きます。
しかし、変化の激しい現代においては、偶然の出来事や新しい経験をどう活かすかが大きな意味を持ちます。
そこで注目したいのが、スタンフォード大学のジョン・クランボルツが提唱した「キャリアの社会的学習理論」です。
この理論は「人は学習し続ける存在であり、計画された偶然をキャリアに変えられる」という考え方を示しており、特に将来にモヤモヤを抱える人にとって実践的なヒントを与えてくれます。
クランボルツが示した4つのキャリア要因
クランボルツは、キャリアの形成に影響する要因を次の4つに整理しました。
- 遺伝的要素と特殊能力(生まれ持った資質)
- 環境条件(社会・家庭・経済など外部要因)
- 学習経験(過去の経験から得たフィードバック)
- 課題アプローチスキル(意思決定や問題解決のスキル)
特に3と4に重点を置いたのが、クランボルツ理論の特徴です。
つまり、環境や生まれつきの資質だけでなく、**「経験から何を学ぶか」「どのように意思決定するか」**によってキャリアは大きく変わっていく、という視点です。
学習経験 ― 道具的学習と連合的学習
人は日々、行動とその結果から学習しています。クランボルツはこれを「学習経験」と呼び、2つの種類に分けました。
- 道具的学習
行動に対する周囲からのフィードバックによる学習。
例:接客で「ありがとう」と感謝されればその行動は強化され、逆に叱られれば行動を改める。 - 連合的学習
予期していなかった出来事と感情が結びつき、新しい興味を形成する学習。
例:病気の家族を助けてくれた医師に憧れ、医療への関心を持つようになる。
👉 ポイントは、人の興味や関心は「経験」によって後天的に変化するということ。
計画的に学習経験を積むことで、新しい興味や選択肢を広げることができます。
課題アプローチスキル ― キャリア選択そのものの力
課題アプローチスキルとは、具体的な目標設定、情報収集、分析、意思決定といった「キャリアを選ぶスキル」そのものです。
これは生まれつき備わっているものではなく、学習経験を通じて磨かれていきます。
👉 つまり、キャリアの正解を「知る」ことよりも、キャリアを選ぶスキルを鍛えることが重要になるのです。
バンデューラの学習理論と自己効力感
クランボルツ理論の基盤には、心理学者アルバート・バンデューラの学習理論があります。
観察学習
人は失敗して学ぶだけでなく、他者の行動を観察して学ぶことができます。
例:赤信号を渡って事故に遭う経験をしなくても、親が信号を守る姿を観察して学ぶ。
自己効力感
バンデューラは「自分はこの行動をできる」という期待感(効力予期)を重視しました。
これは以下の4つの経験から形成されます:
- 成功体験(実際にできた経験)
- 代理経験(他人の成功を見て自分にもできそうだと思うこと)
- 言語的説得(励ましや助言)
- 情動喚起(緊張や不安など感情の影響)
👉 自己効力感が高い人ほど、新しい挑戦を恐れず、キャリアの幅を広げていくことができます。
計画された偶発性 ― 偶然をキャリアに変える
クランボルツが特に強調したのが「計画された偶発性(Planned Happenstance)」という考え方です。
- 偶然の出来事や予期せぬ出会いは、キャリアを形作る大きな要因になる
- 大切なのは「偶然を待つ」のではなく、自ら偶然を掴みに行く姿勢
例えば:
- 飲食業の現場で偶然声をかけられた研修に参加して、新しいスキルを発見する
- 趣味で始めたSNS投稿がきっかけで、副業や新しいキャリアにつながる
👉 計画的に新しい出会いや経験の機会を作ることで、「偶然」を「必然」に変えていくのです。
まとめ ― 変化の時代に必要なキャリア観
従来のキャリア理論は「自分の特性に合う職業を探す」ことを重視していました。
しかしクランボルツは、変化の激しい時代には「学習」と「偶発性の活用」が重要だと説きました。
- 過去の経験から学び、自分の興味を広げる
- 意思決定スキルを磨く
- 偶然の出来事をキャリアに変える
これらを意識することで、予測不能な時代でも自分らしいキャリアを築くことができます。
👉 次の一歩として、「最近の偶然の出来事」を振り返り、それがキャリアにどうつながるかを考えてみてください。そこから新しい可能性が見えてくるはずです。